3.指摘した際に被監査部門とどう向き合うか
戸部様
皆さん、それぞれの組織にあった形での内部監査を実施されていることが分かりました。他に何かコメントやお互いに聞いてみたいことなどはありますか。
本田様
 内部監査事務局としての課題ですが、監査部門も被監査部門も同じ会社ですので、内部監査での発見事項(オブサーベーション)や指摘を素直に実施してくれないのではないか、という懸念があります。私としては、重要ではない発見事項に対しても100%の対応をして欲しいのですが、できる限り100%に近づく形で良いので対応して欲しいという感じで伝えています。また、1年では対応が難しい事項は、「今年は70%まで対応して、来年、また確認するから、段階を踏んで対応してください」という伝え方をしています。皆様は、被監査側に発見事項(オブサーベーション)や指摘の内容をどの様に伝えているのか教えていただけたらと思います。
内部監査事務局としての課題ですが、監査部門も被監査部門も同じ会社ですので、内部監査での発見事項(オブサーベーション)や指摘を素直に実施してくれないのではないか、という懸念があります。私としては、重要ではない発見事項に対しても100%の対応をして欲しいのですが、できる限り100%に近づく形で良いので対応して欲しいという感じで伝えています。また、1年では対応が難しい事項は、「今年は70%まで対応して、来年、また確認するから、段階を踏んで対応してください」という伝え方をしています。皆様は、被監査側に発見事項(オブサーベーション)や指摘の内容をどの様に伝えているのか教えていただけたらと思います。 |
谷上様
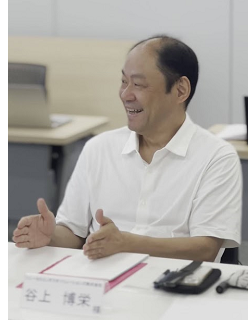 私の場合は被監査部門に「どうすれば良いと思う」と聞いています。まずは自分たちがどうすれば良いのかを、自分たちで考えてもらいます。指摘(不適合)事項とするか、観察事項(オブザベーション)とするかを、被監査部門にまず考えてもらいます。被監査部門として、指摘事項として残すことで改善しやすくなるのであれば指摘事項としますが、自ら率先して改善していただけるのであれば、対応は被監査部門に任せています。「実際の改善につながるようにするためにどうするか」ということを重視しています。
私の場合は被監査部門に「どうすれば良いと思う」と聞いています。まずは自分たちがどうすれば良いのかを、自分たちで考えてもらいます。指摘(不適合)事項とするか、観察事項(オブザベーション)とするかを、被監査部門にまず考えてもらいます。被監査部門として、指摘事項として残すことで改善しやすくなるのであれば指摘事項としますが、自ら率先して改善していただけるのであれば、対応は被監査部門に任せています。「実際の改善につながるようにするためにどうするか」ということを重視しています。
一方、指摘されると消極的になってしまう場合もあります。特に、普段、コミュニケーションが取れていない方に対して指摘事項とすると、相手は身構えてしまいますので、自ら率先して改善してもらうように心がけています。 |
川島様
監査を進める中で、監査員の言いたいことを相手が理解しているなと感じた時はコメントに留め、監査報告書に残す話題、残さない話題を使い分けています。まずは相手を信用することから始めます。ただ、何年も同じ内容の指摘がある場合は、報告書に残すようにしています。前向きに改善してもらうことが大切です。
井上様
谷上さんと共通していますが、監査時に「どうやったらこれをうまく組織として運用できるのでしょうか、考えてみてください」という形で、アドバイスというか、相談に乗る形で進めるようにしています。馴れ合いと言われてしまうかもしれないですが、同じ組織ですから信じて良いと思っています。
木崎様
私も被監査部門に考えていただくっていうことは実践しています。本当にNGの場合は不適合という形にはしていますが、指摘に対する改善や対応期限などは、被監査部門の宿題として、主体的に考えていただくというアプローチをとっています。
4.監査実施後の対応の重要性
戸部様
被監査部門の状況も考えつつ、いかに前向きに改善につなげるか、という所で苦労されているということですね。そのような状況の中で、皆で一緒に良くしていきましょうというスタンスで臨まれているということもわかりました。
さらに、監査チームと被監査部門とのコミュニケーションから、全社のMS全体の見直しや強化につなげていくために、何が必要でしょうか。
井上様
 現在、QMSでの内部監査は、4チームで年2回、基本的に1年間の間に全部門を行っています。まず、全部門の内部監査結果から、指摘の内容を把握し、原因分析をします。その結果、例えば「上流の仕組みを見直す必要がある」という事が分かると、提言も踏まえてトップマネジメントに報告し、必要に応じて仕組みを改善しています。また、トップマネジメントの下に品質管理責任者も設置していますので、仕組み自体に問題がないか、というレビューもしながら進めています。トップマネジメントからは、品質マニュアルについても「この手順は今の業務とあっていないのではないか?」、「この部分を見直ししてみたらどうか?」といった提案を受けることもあるので組織で改善してみよう、という議論にもなります。
現在、QMSでの内部監査は、4チームで年2回、基本的に1年間の間に全部門を行っています。まず、全部門の内部監査結果から、指摘の内容を把握し、原因分析をします。その結果、例えば「上流の仕組みを見直す必要がある」という事が分かると、提言も踏まえてトップマネジメントに報告し、必要に応じて仕組みを改善しています。また、トップマネジメントの下に品質管理責任者も設置していますので、仕組み自体に問題がないか、というレビューもしながら進めています。トップマネジメントからは、品質マニュアルについても「この手順は今の業務とあっていないのではないか?」、「この部分を見直ししてみたらどうか?」といった提案を受けることもあるので組織で改善してみよう、という議論にもなります。 |
本田様
QMSについては、事務局の方だけでなく、全従業員の方が理解しているということでしょうか。
井上様
QMSを全従業員が理解しているかというと、そうとは言い切れないと思いますが、長年、QMSの運用を行っていますので、業務プロセスに落とし込めており、従業員の方々は、QMSとは意識せずに運用していると思います。とはいえ、QMSの周知は進めており、月例の組織内の活動などには、なるべく若手を割り振るよう、依頼しています。
川島様
我々の部門では、全部署の監査データを保有しています。指摘された項目や「グッドポイント」と呼ばれる有用な事案は、全社で共有をして横展開しています。各部門では、共通の指摘や良い事例は参考にしています。
戸部様
内部監査へのトップマネジメントの関与の状況はどうでしょうか。
木崎様
トップマネジメントには年に2回、ISMS運用状況を報告しています。トップマネジメントからはその報告に対するコメントがあり、このコメントを次年度の計画に反映しています。
戸部様
「内部監査」は、被監査部門にとっては日常業務とは別のことのような、重荷に感じている部分もあるのかもしれませんけれども、内部監査を実施しないと何か影響があるでしょうか。
本田様
やはり、PDCAサイクルのバランスが崩れてしまい、長期的には他の部分にも影響が出るように思うので、業務の見直しの機会としての「内部監査」は必要だと思います。
谷上様
「内部監査」では、自部署だけでは気づけないような「グッドポイント」に気づくことができるよい機会として活用しており、有効なツールだと考えています。
川島様
弊社は医療機器を取り扱っており、規制当局からの外部監査を受ける機会がありますので、QMSの内部監査は、外部からの規制目的の外部監査を受ける前提で受けます。ただ、内部監査では大きな指摘はなくても、規制当局からの外部監査では、どうしても指摘が出てしまいます。そのようなことがあると、なぜ、内部監査で指摘事項を事前に検出できなかったのかということが課題になりますので、内部監査レベルを上げることが課題だと感じています。
木崎様
弊社ではISO/IEC27001に準拠したISMSを構築していますが、認証は取得していないので、内部監査が唯一、MSをチェックする機会になっています。その意味で、内部監査はとても重要と感じています
井上様
仮に5年程度、内部監査をやめてしまったとしても、MSは回り続けて、レベルが極端に落ちることはないと思います。しかし、内部監査をやめてしまうと、世代交代が進んだ時点で、品質にも影響が出ると思っています。確かに内部監査は負担が大きいので、業務とのバランスをどのようにするかというのが課題だと感じていますが、業務を見直す機会としては、年1回の監査は必要だと考えています。
戸部様
内部監査が無くなると、長期的には綻びが出てくるかもしれないということですね。被監査部門からの意見は何かありますか
木崎様
監査後は形式的なコミュニケーションに留まってしまっていますが、内部監査を実施することにより責任部門が明確になったと思っています。
谷上様
私が監査員として参加した場合ですが、監査の後に、被監査部門からの、監査に関するヒアリングをする時間をとっています。コミュニケーションがうまくできた部門では様々な意見が出ますが、形式的な監査では何も出てこないですね。監査に関するヒアリングでは、「内部監査はためにならない」、「内部監査は時間の無駄だ」という意見もありますが、それは内部監査でのコミュケーションがうまくいっているから出る意見だと捉えています。

 内部監査事務局としての課題ですが、監査部門も被監査部門も同じ会社ですので、内部監査での発見事項(オブサーベーション)や指摘を素直に実施してくれないのではないか、という懸念があります。私としては、重要ではない発見事項に対しても100%の対応をして欲しいのですが、できる限り100%に近づく形で良いので対応して欲しいという感じで伝えています。また、1年では対応が難しい事項は、「今年は70%まで対応して、来年、また確認するから、段階を踏んで対応してください」という伝え方をしています。皆様は、被監査側に発見事項(オブサーベーション)や指摘の内容をどの様に伝えているのか教えていただけたらと思います。
内部監査事務局としての課題ですが、監査部門も被監査部門も同じ会社ですので、内部監査での発見事項(オブサーベーション)や指摘を素直に実施してくれないのではないか、という懸念があります。私としては、重要ではない発見事項に対しても100%の対応をして欲しいのですが、できる限り100%に近づく形で良いので対応して欲しいという感じで伝えています。また、1年では対応が難しい事項は、「今年は70%まで対応して、来年、また確認するから、段階を踏んで対応してください」という伝え方をしています。皆様は、被監査側に発見事項(オブサーベーション)や指摘の内容をどの様に伝えているのか教えていただけたらと思います。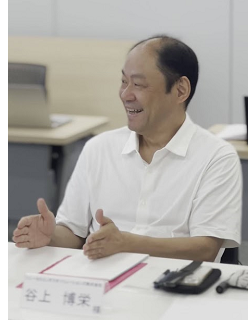 私の場合は被監査部門に「どうすれば良いと思う」と聞いています。まずは自分たちがどうすれば良いのかを、自分たちで考えてもらいます。指摘(不適合)事項とするか、観察事項(オブザベーション)とするかを、被監査部門にまず考えてもらいます。被監査部門として、指摘事項として残すことで改善しやすくなるのであれば指摘事項としますが、自ら率先して改善していただけるのであれば、対応は被監査部門に任せています。「実際の改善につながるようにするためにどうするか」ということを重視しています。
私の場合は被監査部門に「どうすれば良いと思う」と聞いています。まずは自分たちがどうすれば良いのかを、自分たちで考えてもらいます。指摘(不適合)事項とするか、観察事項(オブザベーション)とするかを、被監査部門にまず考えてもらいます。被監査部門として、指摘事項として残すことで改善しやすくなるのであれば指摘事項としますが、自ら率先して改善していただけるのであれば、対応は被監査部門に任せています。「実際の改善につながるようにするためにどうするか」ということを重視しています。 現在、QMSでの内部監査は、4チームで年2回、基本的に1年間の間に全部門を行っています。まず、全部門の内部監査結果から、指摘の内容を把握し、原因分析をします。その結果、例えば「上流の仕組みを見直す必要がある」という事が分かると、提言も踏まえてトップマネジメントに報告し、必要に応じて仕組みを改善しています。また、トップマネジメントの下に品質管理責任者も設置していますので、仕組み自体に問題がないか、というレビューもしながら進めています。トップマネジメントからは、品質マニュアルについても「この手順は今の業務とあっていないのではないか?」、「この部分を見直ししてみたらどうか?」といった提案を受けることもあるので組織で改善してみよう、という議論にもなります。
現在、QMSでの内部監査は、4チームで年2回、基本的に1年間の間に全部門を行っています。まず、全部門の内部監査結果から、指摘の内容を把握し、原因分析をします。その結果、例えば「上流の仕組みを見直す必要がある」という事が分かると、提言も踏まえてトップマネジメントに報告し、必要に応じて仕組みを改善しています。また、トップマネジメントの下に品質管理責任者も設置していますので、仕組み自体に問題がないか、というレビューもしながら進めています。トップマネジメントからは、品質マニュアルについても「この手順は今の業務とあっていないのではないか?」、「この部分を見直ししてみたらどうか?」といった提案を受けることもあるので組織で改善してみよう、という議論にもなります。