4.審査登録機関への質問
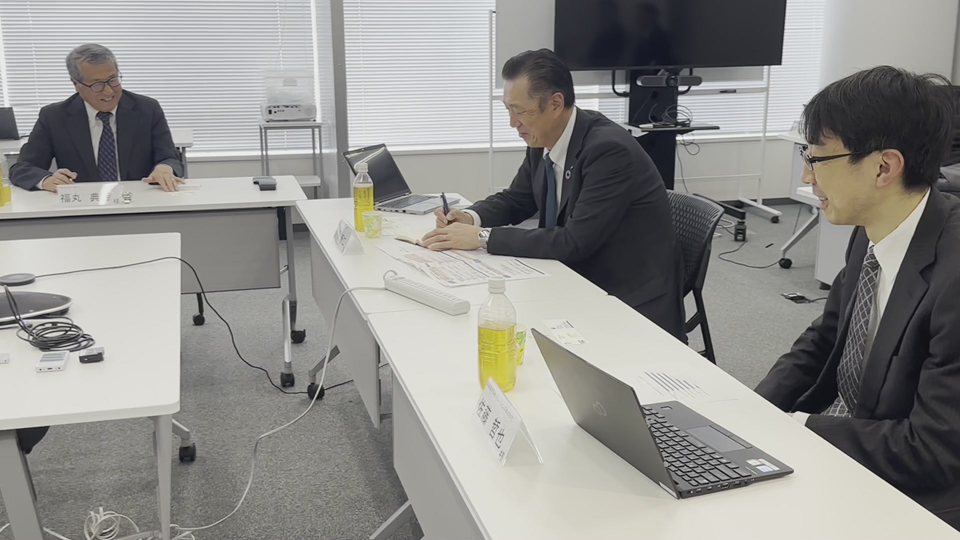 4.1 企業に所属している審査員について
福丸様
4.1 企業に所属している審査員について
福丸様
ありがとうございます。それでは、大日向さんと平野さんから、審査登録機関の方々に何か聞きたいことはありますでしょうか。
大日向様
企業に勤めている審査員が来ることを受審組織側が嫌がることはありますか。契約で守秘義務はあると思いますが、そのような審査員に組織の内部を見られることを嫌う企業もあるのではないかと感じています。
伊藤様
まず、当然ですが、お客様と利害関係が発生するような審査員は派遣できません。一方で、審査では専門性が必要という面もありますので、受審組織によっては「仕事やプロセスが分かる、同じ業界の人を派遣して欲しい」と言われるケースもあります。そのため、企業に勤めているからといって受審組織から忌避される、とは一概には言えないと思います。
私の感触としては、企業に現役で務めている方は最新の知見も持っているので、絶対良いと思います。専門性が高いマネジメントシステムを審査するなら、現在の仕事を知っている審査員の方が良いと思います。
佐藤様
私どもでは、派遣する審査員の略歴を事前に受審組織に提示し、受審組織に確認をいただいています。ただ、ライバル会社に所属しているような審査員は、派遣の検討の段階で対象から外すようにしています。また、最近は若い審査員の要望が多いと感じています。この傾向は、現場を離れて時間が経った審査員よりも、なるべく現役か、現役に近い審査員に来てほしいというニーズの現れだと思っています。利害関係は当然、意識しますが、受審組織は、企業に所属しているような、現役に近い方を期待していると考えています。
4.2 審査活動で苦労する点について
平野様
受審組織から見てこんな審査員がいて困ったというケースをたまに耳にすることがありますが、逆に、審査員側から苦労されたケースはありますでしょうか。
伊藤様
審査現場で直面した困りごととしては、トップインタビューの際に、経営者の方からは「どんどん指摘してください」と言われたのですが、事務局の方が指摘を受けいれてくれず、結果として審査での指摘がトップの方に届かないというケースがあり、苦労しました。
佐藤様
初回会議では、「受審組織と審査員とは対等の立場です」とお話しています。この言葉は、従来は、「審査員は偉いわけはない」ということを意識してもらうために言っていたのですが、最近は逆に、受審組織の方から審査員に対して強い口調で対応するというケースも出てきました。審査とは、規格を共通言語にして、受審組織に対して年に一回行う定期検診のようなものだと考えています。受審組織と審査員とが、改善の機会や適合性の確認などを対等な立場で共有する場だと思っていますが、そのような点で、「対等」という言葉の意味にも変化が生じていると感じています
大日向様
 審査員の持つ専門性と異なる業種、業態の企業の審査は難しいのではないかと思っています。弊社では大工の専門学校の運営もしており、その学校に鉄鋼業界出身の審査員の方が審査に来られましたが、審査がどうもかみ合わなかったということがありました。やはり、ある程度、審査員がその業界に深く関わった経験のある方でないと、受審組織のプロセスなどが分からないのではと思っています。マネジメントシステムの運用を審査するという意味では、他の業界出身の審査員の方でも審査できるとは思いますが、審査登録機関として審査員を派遣する際にはどのように検討しているのでしょうか。
審査員の持つ専門性と異なる業種、業態の企業の審査は難しいのではないかと思っています。弊社では大工の専門学校の運営もしており、その学校に鉄鋼業界出身の審査員の方が審査に来られましたが、審査がどうもかみ合わなかったということがありました。やはり、ある程度、審査員がその業界に深く関わった経験のある方でないと、受審組織のプロセスなどが分からないのではと思っています。マネジメントシステムの運用を審査するという意味では、他の業界出身の審査員の方でも審査できるとは思いますが、審査登録機関として審査員を派遣する際にはどのように検討しているのでしょうか。
|
佐藤様
専門性という点では、一番よいのは同業他社出身の方となりますが、そのような方の場合、利害関係者となってしまうこともあります。そのため、専門性を突き詰めることには限界があると思っています。審査員が業界について知っているのは当然のことですが、マネジメントシステム規格をベースに、「素朴な疑問」を投げかけることで、「客観的に見たらおかしいのかもしれない」「こういうものだと思っていたが、ひょっとしてちょっと違うのでは」といった気づきを引き出せるのが、内部監査ともまた違う第三者審査によるメリットだと思っています。専門的な部分は内部監査で確認し、第三者審査では、一歩引いた目線での、端(はた)から見た審査として意識していくのがよいと思っています。
伊藤様
佐藤さんがおっしゃったように、違う業界出身の審査員からの審査の方が客観的な視点での審査になると考えています。一方、受審組織は、業界のことが分かった審査員に来てほしいという要望が多いように感じます。そのような場合は、なるべく業界の専門性を持った審査員を派遣するようにしますが、それが難しい場合、コミュニケーション能力が高い方をアサインするようにしています。
また最近、難しくなっているのが専門性です。現在の審査のルールでは、審査員は、審査先の業界の専門性を持つことが必須となっています。審査員も、最初は1、2種類の専門性しかないのですが、審査員に対してどのようにして専門性を付与していくのか、ということに悩んでいます。専門性のない審査員には、審査前に業界のガイドを読ませる、何らかの教育を行う、何度かOJT審査を行うなどの対応をしています。ですので、転職の経験が多い方は、多くの専門性を持った審査員になるのではないかと思っています
福丸様
審査員の専門性は非常に難しいですね。例えば、病院、原子力関連産業などもそうですが、建設業界も、法規制が多く、審査の際に専門性が要求されますよね。
伊藤様
建設業界は、受注の形態が一般的には分かりにくいと思いますので、そこを理解している必要はあると思います
福丸様
先ほど、佐藤さんもおっしゃっていましたが、マネジメントシステムの審査なので、基本的にはマネジメントシステムの運用状況を見るのですが、製品実現のプロセスを確認するには、ある程度の知識は必要になってくると思います。あとは「慣れ」ということも大事で、いろいろな審査を経験すると、審査の勘所が掴めてくると思います。
伊藤様
佐藤さんが先ほど、「好奇心」とおっしゃっていましたが、分からないことがあればお客様に聞けばよいと思っています。例えば、自分の出身とは全く異なる業界の審査で、設計の資料を見ても全く分からないような状況でも、「何が肝心なのですか」と聞いてしまえばよいと思います。「好奇心」を持ってお客様に質問ができるようになると、一人前の審査員だと思います。
4.3 審査員ビジネスの将来性について
平野様
 最近、企業によってはISO離れという状況も増えてきているように感じていますが、そのような状況で、将来的に審査登録機関で審査員として活動することについてはどの様に考えられているのでしょうか。
最近、企業によってはISO離れという状況も増えてきているように感じていますが、そのような状況で、将来的に審査登録機関で審査員として活動することについてはどの様に考えられているのでしょうか。
|
伊藤様
まずは、審査員をやりたいのか、やりたくないのかという点があるように思います。審査員として活躍している方には、80歳を超えた方もいらっしゃいますので、この年齢まで活躍できる仕事というはめったにないと思います。また、企業に行って審査を行い、適切な指摘をすることで企業にご満足いただける仕事はなかなかないと思います。そのような点で、60歳を過ぎて経験豊富な方の仕事としては大変魅力のある仕事だと思います。
佐藤様
審査員という仕事は、本当に一生涯付き合えるセカンドキャリアだと思っています。その意味ではとても魅力的です。また、最近、審査員の面接の中で、社会貢献という話をされる方もおられます。今までは会社のために働いてきたが、これからは社会のために働きたいとなった時に、マネジメントシステムの審査では、自分の持つ知見を活かして受審組織の改善に繋げることができます。そのような点では、審査員という仕事は、単に収入が得られるだけではなく、社会貢献もできるという満足感も合わせて得られる魅力的な職業だと思っています。
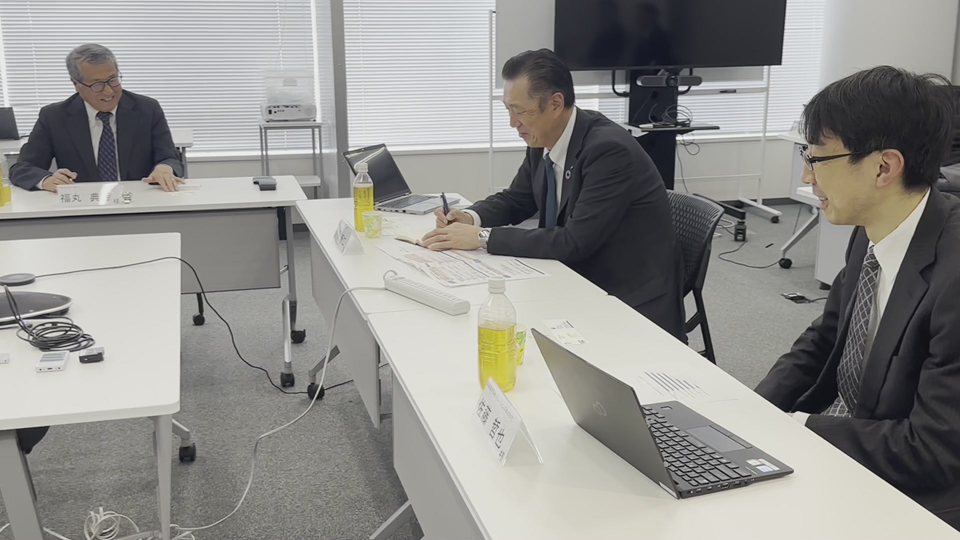
 審査員の持つ専門性と異なる業種、業態の企業の審査は難しいのではないかと思っています。弊社では大工の専門学校の運営もしており、その学校に鉄鋼業界出身の審査員の方が審査に来られましたが、審査がどうもかみ合わなかったということがありました。やはり、ある程度、審査員がその業界に深く関わった経験のある方でないと、受審組織のプロセスなどが分からないのではと思っています。マネジメントシステムの運用を審査するという意味では、他の業界出身の審査員の方でも審査できるとは思いますが、審査登録機関として審査員を派遣する際にはどのように検討しているのでしょうか。
審査員の持つ専門性と異なる業種、業態の企業の審査は難しいのではないかと思っています。弊社では大工の専門学校の運営もしており、その学校に鉄鋼業界出身の審査員の方が審査に来られましたが、審査がどうもかみ合わなかったということがありました。やはり、ある程度、審査員がその業界に深く関わった経験のある方でないと、受審組織のプロセスなどが分からないのではと思っています。マネジメントシステムの運用を審査するという意味では、他の業界出身の審査員の方でも審査できるとは思いますが、審査登録機関として審査員を派遣する際にはどのように検討しているのでしょうか。 最近、企業によってはISO離れという状況も増えてきているように感じていますが、そのような状況で、将来的に審査登録機関で審査員として活動することについてはどの様に考えられているのでしょうか。
最近、企業によってはISO離れという状況も増えてきているように感じていますが、そのような状況で、将来的に審査登録機関で審査員として活動することについてはどの様に考えられているのでしょうか。